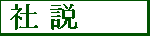
ついに恐れていた事態に発展した。インドに続いてパキスタン
も、国際世論を押し切り地下核実験を強行した。パキスタンは「外
部の攻撃の脅威を考慮」し、全土に非常事態を宣言している。中距
離弾道ミサイルへの核弾頭搭載もあり得る。再実験の可能性も否定
していない。南アジアの核状況は一触即発の危機にある。被爆地・
広島を抱える私たちは、深刻な事態を好転させるために、出来るこ
とから行動に移したい。
パキスタンのシャリフ首相は、インドから「核が突き付けられ
た」事態に対し、国家の安全保障のために核実験を行った、と発言
した。そして、私たちが懸念したように「インドがきちんと罰せら
れれば、われわれは決断をする必要はなかった」と、国際社会のイ
ンドへの制裁が不十分だったことを実験強行の理由に挙げた。両国
は大戦後も三度、戦火を交えただけでなく、イスラム教とヒンズー
教という宗教的対立もある。抜き難い不信感が問題を一層こじらせ
ている。
世界の核開発に詳しい米国の科学国際安全保障研究所(ISI
S)によると、パキスタンは核兵器約十発分の高濃度ウランを保
有、二〇〇五年には約六十発分の保有能力を持つだろうという。一
方のインドは、同時期に百六発の保有能力を持つと分析している。
カシミール帰属をめぐって敵対する両国に複数の核兵器が存在する
のである。人類の上に三度目の核兵器が投下される可能性が、現実
味を帯びてきた。
核五大国だけに保有を認めることで成り立つ核拡散防止条約(N
PT)や、包括的核実験禁止条約(CTBT)による核管理体制
は、両国の核開発競争の過熱で崩壊の危機に直面している。こうし
た事態が、いまも「核カード」を手放していない朝鮮民主主義人民
共和国(北朝鮮)や、核疑惑国イスラエル、さらに中東諸国への
「核の連鎖」につながらないか、懸念される。打開する方向の一つ
は、核大国自身による核廃絶プログラムづくりにある。日本政府も
私たちも、インド、パキスタンを非難するだけでなく、核大国にも
働きかけなければならない。
テレビを通じて伝えられるインド、パキスタン両国民のヒステリ
ックな熱狂ぶりも気になる。被爆地の声など耳に入りそうもない。
それどころか、シャリフ首相は「広島、長崎の二の舞いにはなりた
くない」と、核武装を正当化した。
私たちは被爆体験にもとづく核廃絶への説得力ある論理を再構築
する必要がある。最近、刊行された「丸山眞男と広島」(林立雄
編)によると、被爆者でもある政治学者・丸山氏が、ある私信に、
原爆体験が重ければ重いほど、体験をふりまわすような日本的風土
はきらいだ、と表明、「被爆者ヅラをするのがいや」で、原爆手帳
の申請もしていない、と書いている。「被爆者ヅラ」という言葉に
ショックを覚える。これまでも体験を伝えようとする思いが、こう
した見方に泣かされたこともある。
しかし、被爆地からの発言や運動が、一部にせよ、「押しつけ」
に映るということは、心する必要もあろう。国際的な集いでも、被
爆地からの核廃絶を求める発言に対して、「それで、あなたは何を
しているのか」との問い掛けが多くなってきたという。言葉だけで
なく実現への行動が求められている。例えば広島は、米国などに核
軍縮を働きかけるよう、日本政府にどれだけ求めてきたか。
被爆地・広島はあらためて「何ができるか」を考える必要があ
る。今やっていることを、より説得力のあるものにする工夫も求め
られる。「座り込み」は対外的に十分な効果を上げているか。顔ぶ
れもマンネリ化し、若い人の参加も少ない現状を打開する方法はな
いのか。より多くの市民の思いを核大国や新たな核保有国に伝える
には、どんな行動を組み合わせていったらいいのか。市民の思いも
言語の壁に阻まれている。それらを翻訳したり、郵送する手伝いが
出来る公的施設は考えられないか。一館一国運動を成功させた公民
館の経験は生かせないか。
取りあえず、パキスタンに対するインドの対抗措置が心配であ
る。これをなんとか阻止したい。さもないと対立はエスカレートす
るばかりであろう。両国の国民は核兵器について十分な知識を与え
られているとは思えない。せいぜい「でっかい爆弾」ぐらいの認識
のようだ。国民に核への批判を育てるには、その国の内側から認識
を広げていくしかない。
広島市はインドで原爆展を開いてきた。現地で協力した市民もい
る。広島県原水禁は来月、被爆者らをインド、パキスタンに派遣す
る予定だ。「一回や二回でどうこうなるものでもない。まず、相手
の言うことをよく聞くことだ」と横原由紀夫常任理事。こうした動
きを通じて両国のオピニオンリーダーを広島に呼んで、核大国も交
えた話し合いの場を持つことは可能だろう。新設の広島平和研究所
や広島平和文化センターなどが働けそうな分野だ。そのための費用
を被爆者や市民から募ることも考えられる。
あるいは四百五十六都市にまで広がった世界平和連帯都市市長会
議のメンバーに、国際世論喚起を働きかけるのも方法だろう。イン
ドには五都市、パキスタンにも二都市のメンバーがいる。
気落ちすることなく、あせることなく、行動を積み重ねたい。

|